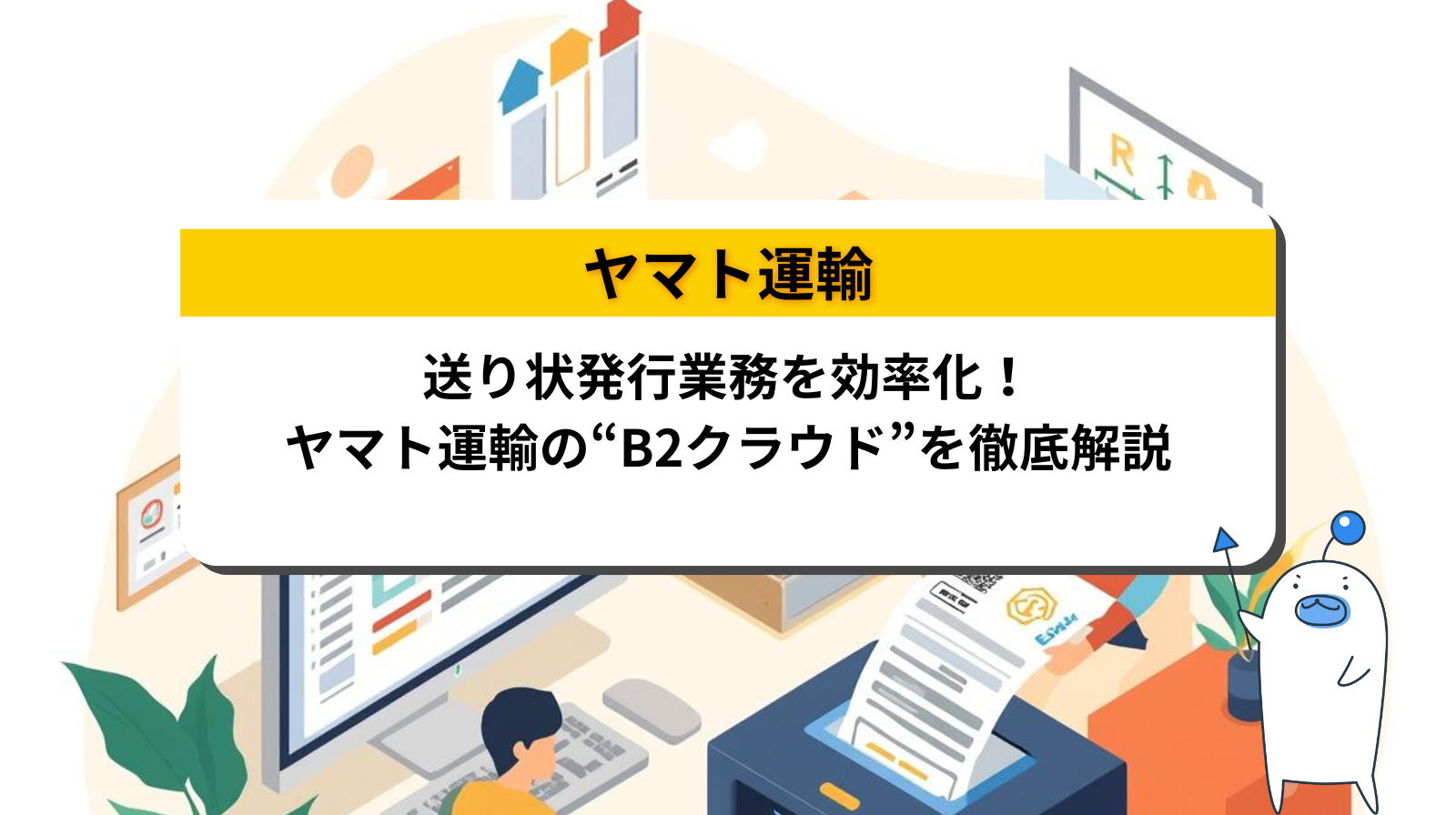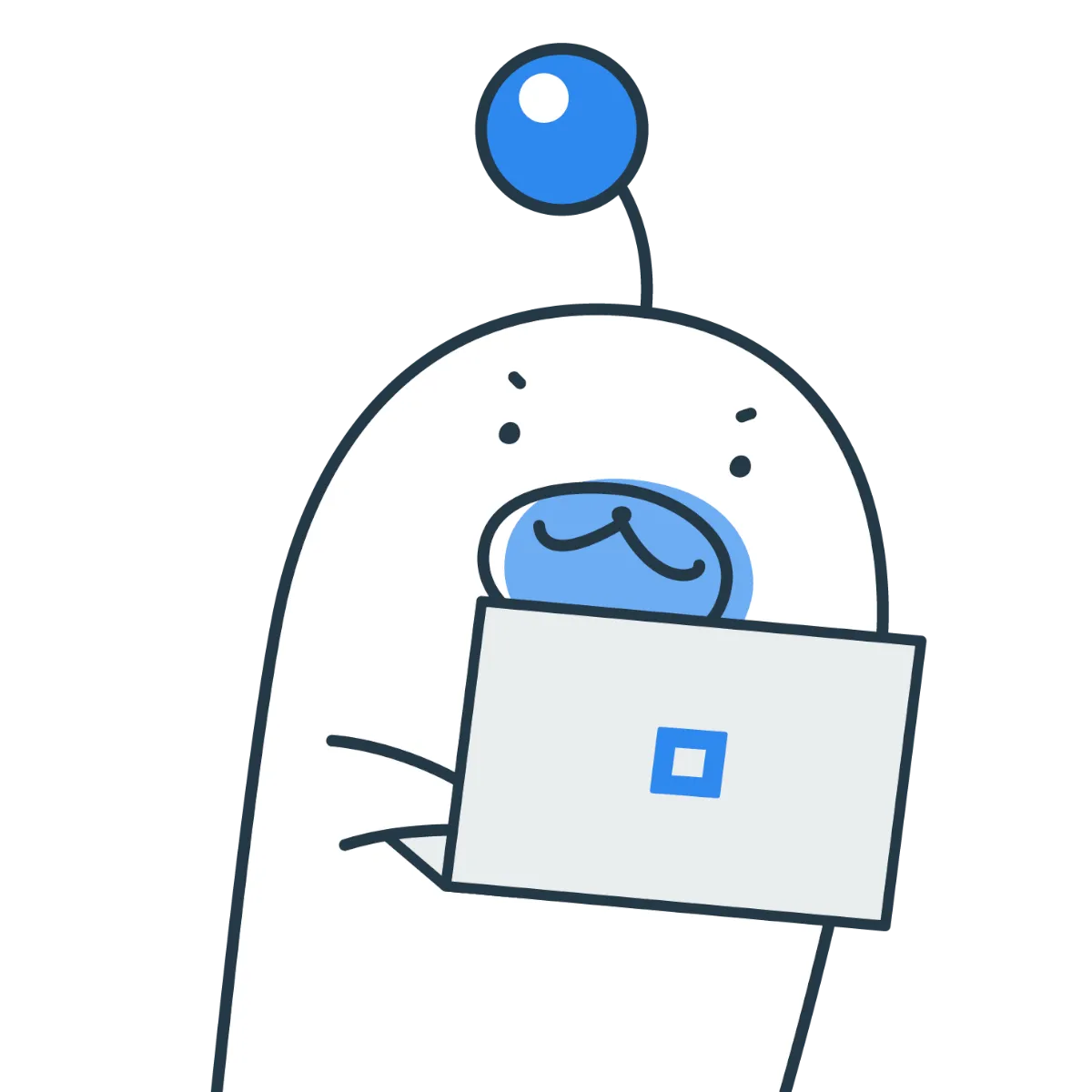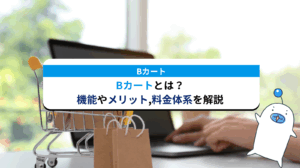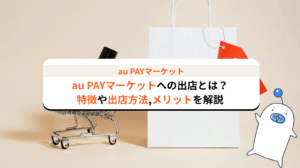EC事業や通販業務において、送り状作成作業の負担に悩む事業者は多く存在します。 受注件数の増加とともに手書きでの送り状作成は大きな負担となり、作業時間の増大やミスの発生といった課題が深刻化している現状があります。
ヤマト運輸が無料で提供する「送り状発行システムB2クラウド」なら、これらの課題を根本的に解決可能です。 本記事では、B2クラウドの概要からメリット、導入方法までわかりやすく解説いたします。
- B2クラウドは送り状作成の手間を大幅に削減できる無料システムである
- API連携により受注から出荷まで自動化が実現できる
- 50万社を超える導入実績で信頼性が高いサービスとなっている
そもそもB2クラウドとは何なのか
ヤマト運輸が提供するB2クラウドについて、基本的なサービス内容と特徴を見ていきましょう。
送り状を簡単に作れるWebシステム
ヤマト運輸が法人・個人事業主向けに提供している宅急便やネコポスの送り状・宛名ラベル作成システムです。 パソコンとプリンターがあれば、専用の送り状用紙に直接印刷できるWebサービスとして設計されています。
システムの特徴は、ExcelやCSV形式のファイルから配送先データを一括で取り込み、送り状を無駄なく発行できることです。 一括発行では最大1,000件まで対応しており、個別入力による1件ずつの発行にも対応しているため、事業規模や業務フローに合わせた柔軟な運用が可能となります。
対応する配送サービスは宅急便、クール宅急便、宅急便コンパクト、ネコポス、クロネコゆうパケットなど、ヤマト運輸の主要サービス全般をカバー。 発払・着払の両方に対応し、国際宅急便にも利用できる充実した機能を備えています。
50万社が選んだ実績
2017年5月のサービス開始以来、着実に利用企業数を伸ばし続け、現在では50万社を超える事業者に導入されている実績があります。
多くの企業に選ばれる理由として、ヤマト運輸という老舗物流会社が運営する安心感が挙げられるでしょう。 システムの安定性やセキュリティ面での信頼性は、日々の業務を支える基盤として欠かせない要素です。
また、継続的な機能改善により、2024年6月にはB2クラウドAPIの公開も実現しました。 ユーザーのニーズに応じたサービス向上を続けており、長期利用においても安心できる環境が整備されています。
費用をかけずに使える無料サービス
基本機能を完全無料で利用できることがポイントの1つとなっています。 初期費用や月額利用料は一切発生せず、登録完了後すぐに送り状発行業務を開始可能です。
無料プランでも充実した機能を利用でき、 発行済みデータの検索機能も備わっており、過去の出荷データもシステム上で確認できるため、送り状控えの紙保管が不要になるメリットもあります。
有料オプションとして、お届け予定eメールや投函完了eメールなどの通知サービスも用意されています。 基本機能で十分な場合は費用をかけることなく、必要に応じてオプションを追加する柔軟な料金体系が採用されている仕組みです。
B2クラウドを使うとどんな良いことがあるのか
B2クラウド導入により得られるメリットについて解説します。
送り状作成が驚くほど早くなる
手書きによる送り状作成と比較すると、B2クラウドの業務改善効果は劇的な変化をもたらします。 従来の手書き作業では1件ずつ時間をかけて記入していた送り状作成が、データ一括取り込みにより大幅に短縮される仕組みです。
特に受注件数が多い繁忙期において、その成果は顕著に現れます。 大量の送り状を短時間で処理できることで、他の重要業務に集中できる時間が生まれ、全体的な業務改善につながります。
さらに、送り状発行後の配送番号管理も自動化。発行データはCSVやExcel形式で出力でき、各ECモールやカートシステムへの配送番号反映作業も無駄なく行える環境が整います。
手作業によるミスが激減する
手書きによる送り状作成では、文字の読み違いや記入漏れ、宛先間違いなどのヒューマンエラーが避けられません。 B2クラウドを利用することで、ミスを根本的に防ぐことが可能です。
データベースからの自動転記により、住所や氏名の転記ミスがなくなります。 システム内でのデータ整合性チェック機能により、配送先情報の正確性が向上し、結果として再送や問い合わせ対応の手間が削減される効果があります。
品質向上は顧客満足度の向上にも直結する要素となります。 正確な配送情報により配送遅延が減少し、顧客からの信頼獲得につながる基盤を構築できるでしょう。
過去の配送データが一目でわかる
発行した送り状データがすべてシステム上に蓄積され、過去の配送実績を簡単に検索・確認できます。 配送状況の追跡も一括で行え、個別に追跡番号を入力する手間が不要。
データの一元管理により、配送業務の分析と改善も可能になります。 配送先別の配送頻度や配送パターンの把握など、業務改善に役立つデータの抽出が容易な環境です。
紙ベースの送り状控えを保管する必要がなくなることで、物理的な保管スペースの削減とペーパーレス化も実現可能。 環境負荷軽減とコスト削減の両面でメリットが得られます。
B2クラウドでできることと便利な機能
B2クラウドを活用し、日常業務で活用できる実用的な機能を中心に紹介します。
ExcelやCSVファイルから一瞬で送り状作成
ExcelやCSV形式のファイルからの外部データ取り込みが核となる機能です。 ECサイトや販売管理システムから出力された受注データを、そのままB2クラウドにアップロードして送り状発行に利用できます。
取り込み可能な項目は、お届け先情報、依頼主情報、荷物情報、配送指定日時など送り状作成に必要なすべての項目をカバー。 データの項目名が異なる場合も、システム上でマッピング設定を行うことで柔軟に対応します。
各種販売管理ソフトとの連携機能も用意されており、 大塚商会のSMILE販売BS2、弥生販売、OBCの商奉行、筆まめクラウドなどとの連携により、さらなる業務改善が実現可能な仕組みです。
最大1,000件まで一気に処理できる一括発行
1回の操作で最大1,000件の送り状を一括発行できる機能を備えています。 この一括発行機能により、大量の発送業務でも無駄のない処理が可能となります。
発行処理は安定しており、大量データでも確実に送り状が生成される設計です。 処理中は他の作業を並行して行えるため、業務の停滞を最小限に抑えることが可能となります。
発行された送り状は連続して印刷されるため、印刷後の仕分け作業も円滑に進められます。 印刷順序の指定や条件による並び替えも可能で、ピッキング作業との連動を考慮した運用が行える環境です。
あらゆる配送サービスに対応した送り状
宅急便の基本サービスに加え、クール宅急便、宅急便コンパクト、ネコポス、クロネコゆうパケット、クロネコゆうメール、国際宅急便まで幅広い配送サービスに対応しています。
各サービスに応じた専用の送り状フォーマットが用意されており、商品の種類や配送条件に適した配送方法を選択できます。 発払・着払の選択や、タイムサービスの指定も可能な仕組みです。
コレクト(代金引換)サービスにも対応しており、EC事業者にとって重要な決済手段である代引き配送の送り状も円滑に作成できます。
API機能で実現する業務の完全自動化
2024年6月に公開されたAPI機能について解説します。システム連携による業務自動化の可能性について見ていきましょう。
待望のAPIがついに登場
ヤマト運輸は2024年6月12日から、EC事業者の要望に応えてB2クラウドAPIを正式に公開しました。 このAPI公開により、B2クラウドの機能をより柔軟に活用できるようになりました。
B2クラウドAPIは、既存のEC業務関連システムから直接送り状発行を行うためのWeb-APIです。 従来はB2クラウドの画面を別途開いて操作する必要がありましたが、API連携により自社システム上で送り状発行が完結する仕組みとなります。
API利用により、送り状発行済データの連携も自動で行われるため、手動でのデータ移行作業が不要です。 これまでEC事業者が抱えていた「システム間の切り替え作業」という課題が解決されました。
既存のECシステムと直接つながる
B2クラウドAPIの最大のメリットは、EC業務システムとの直接連携により業務フローがシームレスになることです。 受注管理システム、在庫管理システム、顧客管理システムなど、既存のシステムからダイレクトに送り状発行が可能となります。
連携により、受注データの入力から送り状発行、配送番号の反映まで、一連の作業が自動化される環境です。 オペレーターの作業は最小限に留まり、ヒューマンエラーのリスクも大幅に軽減されます。
特に複数のECモールに出店している事業者にとって、各モールの受注データを統合して一括処理できることは大きな業務改善につながります。
注文から発送まで人の手を介さない運用
API連携により実現されるのが、受注から出荷まで完全に自動化されたシームレス運用です。 顧客からの注文受付と同時に、在庫確認、送り状発行、配送手配が連動して実行されます。
このシームレス運用により、注文から出荷までのリードタイムが大幅に短縮される効果があります。 迅速な出荷対応は顧客満足度の向上に直結し、リピート率の向上や口コミによる新規顧客獲得にもつながるでしょう。
システム間のデータ連携が自動化されることで、データの整合性も保持が可能です。 注文情報、在庫情報、配送情報が常に同期されており、業務判断に必要な正確な情報をリアルタイムで把握できる環境が構築されます。
B2クラウドを始めるための準備と手続き
B2クラウドを実際に導入するための手順について見ていきましょう。
まずはヤマトビジネスメンバーズに登録
B2クラウドを利用するためには、まずヤマトビジネスメンバーズへの登録が必要となります。 ヤマトビジネスメンバーズは、ヤマト運輸が法人・個人事業主向けに提供している総合サービスプラットフォームです。
登録自体は無料で行えますが、利用には前提条件があります。 ヤマト運輸との掛売り契約(未収契約・請求書払い)を締結している事業者のみが対象となる仕組みです。
既存の掛売り契約がある場合は、お客さまコードと仮パスワードがあればすぐに利用可能です。 契約がない場合は、まず法人契約の申し込み手続きを行う必要があります。

掛売り契約の申し込みと審査
B2クラウド利用の前提となる掛売り契約は、ヤマト運輸の法人営業担当者との協議により進められます。 契約には一定の審査があり、事業内容や取引予定量などの情報提供が求められます。
契約締結後、ヤマトビジネスメンバーズのログインに必要な情報が提供される流れです。 この情報を使用して初回ログインを行い、本登録手続きを完了させます。
掛売り契約により、送料の後払い決済が可能となり、月次での請求書発行による支払いシステムが利用できます。 都度の送料支払いが不要となり、経理処理も円滑化されるでしょう。
システム設定と専用用紙の準備
ヤマトビジネスメンバーズへの本登録完了後、サービス一覧からB2クラウドを追加します。 「サービス一覧」から「送り状発行システムB2クラウド」を選択し、「メニューに追加する」をクリックするとサービスが有効化される仕組みです。
次に、送り状発行に必要な専用用紙を入手する必要があります。 B2クラウド専用の送り状用紙はヤマト運輸から無償で提供され、必要枚数に応じて配送されるでしょう。
プリンターの設定確認も必要な作業となります。 B2クラウドはレーザー、インクジェット、サーマルプリンターに対応しており、使用するプリンターに適した設定を行うことで、正確な印刷が可能です。
利用前に知っておくべき注意点
B2クラウド利用時の注意すべき点について解説します。
誰でも使えるわけではない利用条件
B2クラウドの利用には明確な条件があり、すべての事業者が利用できるわけではありません。 最も重要な条件がヤマト運輸との掛売り契約の締結となります。 個人の荷主や現金払いでの利用は対象外という制限があります。
対象ユーザーは法人および個人事業主に限定されている仕組みです。 一般個人の利用は想定されておらず、事業としての配送業務を行う事業者向けのサービスという位置づけとなります。
継続的な取引を前提としており、スポット的な利用には適していません。 定期的な配送業務がある事業者に最適化されたシステム設計です。
ヤマト運輸以外の配送会社は使えない
B2クラウドで発行できる送り状は、ヤマト運輸が提供するサービスに限定されます。 他社の宅配便やメール便サービスには対応していないため、複数の配送業者を利用している場合は別途対応が必要となります。
| 配送業者 | 専用システム | 主な対応サービス |
|---|---|---|
| ヤマト運輸 | B2クラウド | 宅急便・ネコポス・クール宅急便 |
| 佐川急便 | e飛伝シリーズ | 飛脚宅急便・飛脚メール便 |
| 日本郵便 | ゆうプリR | ゆうパック・レターパック |
佐川急便であればe飛伝シリーズ、日本郵便であればゆうプリRなど、各配送業者が独自の送り状発行システムを提供しています。 複数業者利用の場合は、それぞれのシステムを併用する運用が必要です。
国際配送については、ヤマト運輸の国際宅急便のみが対応範囲となります。 EMS(国際スピード郵便)やFedEx、DHLなどの国際宅配便には対応していません。
システム利用時の制限とメンテナンス
B2クラウドには1回あたりの処理件数制限があり、一括発行では最大1,000件までとなっています。 それ以上の大量発送が必要な場合は、複数回に分けて処理する必要がある仕組みです。
システムの利用時間帯にも制約があり、メンテナンス時間中は利用できません。年末年始や大型連休中は一部機能が制限される場合があるため、事前の確認が必要です。
ブラウザ環境についても推奨環境が設定されており、2024年4月以降はFirefoxが推奨環境から除外されています。 安定した動作のため、推奨ブラウザでの利用が求められる環境です。
まとめ
ヤマト運輸が提供するB2クラウドは、EC事業者や通販事業者の業務改善に大きく貢献するサービスです。手書きによる送り状作成から解放され、データ一括取り込みによる大幅な作業時間短縮を実現できます。
50万社を超える導入実績が示すように、システムの信頼性と利便性は多くの事業者に評価されている現状があります。2024年6月に公開されたB2クラウドAPIにより、既存システムとの連携がさらに強化され、受注から出荷までの完全自動化が可能となりました。